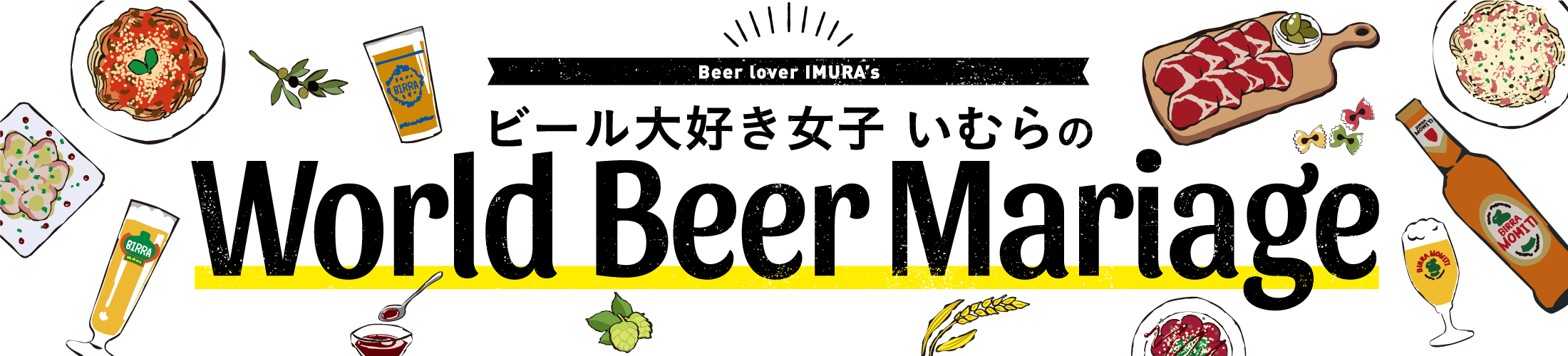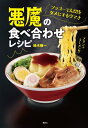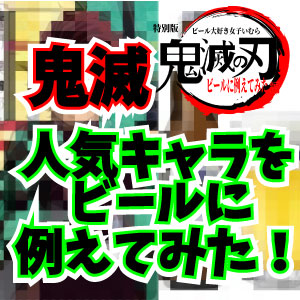フードペアリング界隈で話題沸騰中の本が、日本語版で発売されました。
その名は
『香りで料理を科学するフードペアリング大全 分子レベルで発想する新しい食材の組み合わせ方』
です!!
タイトルだけで
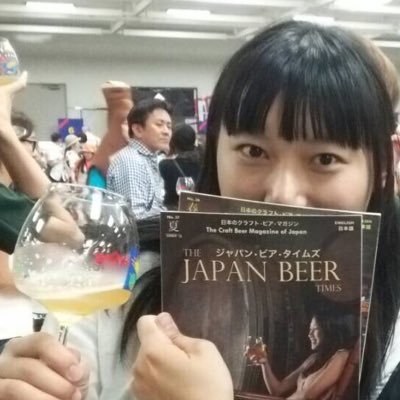
てなりますね。
私がこの本を知ったのは、ベルギービールプロフェッショナルの講座案内でした。
「こんな本が出たので、内容を読み解くオンライン講座をします。未購入でも参加OK!」なんて言われたら、“申し込む”をクリックするしかないですよね。
オンライン講座を受けたあとは、「この本は絶対手元に置いときたい!!」という強い思いに駆られ、本屋さんをハシゴしちゃいました。。

端的に言うと、この本は食材に含まれる香りの辞典なんですよ!!
特殊な機械を使って、あらゆる食材にどのような香り成分が、どのくらい入っているかを調べたものが列挙されています!
前半の30ページ程には
最初に書かれている内容
・香りとは何か?
・おいしいとはどういうことか?
・香りの分析表の見方
などなど、興味深いトピックについて詳細に記されています。
そしてあとの300ページ程は、食材ごとの香りの分析表となっています!
中にはピルスナーやランビックなども載っていますよ!!
「あーたしかに、これってこんな香りするよね」というものから、「え!?これってそんな成分あんの!?」という機械分析ならではのものもあります。
フードペアリングを考える方はもちろん、料理人やソムリエさんにも是非手に取っていただきたいですね!
今回は、前半のトピックの中から
〇「おいしい!」に占める“香り”の重要性
〇香りを使ったフードペアリングの仕方について、学んだこと
を個人的に解釈してご紹介します!
必ずしも『フードペアリング大全』と同じ言葉、同じ意見ではないかもしれません。
しかし、誰が読んでも「おいしい組み合わせ」について考えられるヒントになっていると自負しています。
それでは早速、「おいしい」とは何か?から見ていきましょう!!
「おいしい!」に占める“香り”の重要性
食べ物や飲み物は、五感で味わっていますよね。
五感のどれが欠けても、「おいしい!」からは遠ざかってしまいます。
「おいしい」と感じる要素には
「おいしい」と感じる要素
・今まさに身体が欲している栄養素
・慣れ親しんだ安心、安全な味
・伝統的、文化的
の3つがあります。
「身体が欲している」というのはわかりやすいですね。
普段はおいしくない経口補水液も、脱水症状の出ているときに飲めば、水よりおいしく感じます。
人間の体は身体にとって必要な栄養素はおいしく不必要だったり毒素になる栄養素はまずく感じるようにできています!
毒素となるもの(アルコールなど)でも、慣れればおいしく感じてきます。
最初は「お酒なんておいしくない、カシオレしか飲めない〜」と思っていても、
ある日突然「お???ビールっておいしいな??」と気づき、
次第に「ウィスキーは、水を一滴垂らすのがいいんだ!」
「ラストオーダー?それじゃ芋(焼酎)のロックで!」と言い出すようになってきます。
飲酒だったり、ワサビやからしを使うようになるのは、辛いものや苦いものに慣れていったということですね。
また慣れに関して言えば、実家のご飯が一番だと感じたり、奥さんと母親の料理を比べてしまったりしてしまう、ということもありますね。やはり慣れ親しんだ味はおいしく感じるものです。
文化的背景に関しても同じですね。
例えば、ピルスナーと枝豆が合うって、誰が決めました??
味わいだけで言うなら、ドイツ系で色が濃いドゥンケルやシュバルツの方が合うと思いますよ。
ただ人間には「みんなと同じ=安心」という本能があるので、「キンキンのビールと枝豆=おいしい」と刷り込まれてしまうのです。
前置きが長くなってしまいました。。
ここからは、「五感で楽しむ“おいしい”」について、視覚から順番に深掘りしていきます!
視覚
おいしいそうな食べものや盛り付け方を「インスタ映え」「映える」と言いますが、これは大切なんです!
おいしそうに見えるということは、脳が「これは必要な栄養素だ」と判断している、ということですからね。
またおいしそうに見える盛り付けとして「シズル感を出す」というのがあります。

シズル感の例としては
しずる感
①お肉からじゅわ〜っと溢れる肉汁
②温かいお料理から立ち昇る湯気
③冷たいものの容器(ビール缶など)についた結露
④野菜や果物の切り口から、果汁などが滴るフレッシュ感
②と③の温度に関してははわかりやすいですね。
温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷たいうちに食べたり飲んだりした方がおいしいです。
①と④に共通しているのは、水分量の多さ。
これ、実はめっちゃ大切なんですよ!
水分量が多い=新鮮=傷んでないなので、人間は水分量の多い食べ物をおいしいと感じるようにできているんです!
またカラフルな飲食物の方が「インスタ映え」と言われますが、これにも理由があります。
いつもいつも同じ食材のものばかりを食べていると、栄養が偏る可能性があります。
だから、彩り豊かなものを「おいしそう!」と思うように、本能に組み込まれているんですね。
視覚の最後に、「おいしくなさそう」について。。
「不味そう」と感じるからには、何かしら理由があります。
第一に、その食材で当たったことがある、それが嫌いだから……という場合。
人間は何度も失敗しなければ学べない生物ですが、食べ物に関しては生死に関わるので、一発で危険を学習します。
だから、一度「無理!」と思ったものはなかなか克服できません。
第二に、慣れがない場合。
最近、こんな本を買ったんですよ。
ほとんどのページ、見ると食欲が削がれていきます。。
科学的な角度から組み合わせを紹介しているので、興味深い、試してみたいものもあったんですが……
「視覚」という点で見れば、安心・安全だと判断できないもの、慣れていない組み合わせは、おいしそうには見えませんね。。
聴覚
缶ビールを開ける「ぷしっ」という音、

瓶のコルクを抜く「ぽん!」という音、
グラスに注ぐ「とっとっと」という音、
炭酸が弾ける「ぱちぱち」とした爽やかな音……。
思い出しただけで喉が渇いてきましたね!!
音も、「おいしい!」を感じるうえで大切な要素です。
上に書いたような音から、おいしい記憶が思い出されて、「今までのおいしい体験=安心」に繋がります。

お肉が鉄板で焼ける「じゅわ〜っ」という音や、お鍋の「ぐつぐつ」と炊かれる音も、食欲をそそりますね。
また純粋に聴覚が捉える刺激としての音だけではなく、咀嚼したときの触覚と連動した音も「おいしい」の要素になります!
お漬物の「ぽりぽり」音や、クルトンの「さくさく」音、ビールを飲み込んだときの「ごくっ」と喉が鳴るのも、もし聞こえなかったらおいしさ半減です。
触覚
「おいしい」にとって重要な触覚には
「おいしい」にとって重要な触覚
・顎の筋肉がどのように動いたか(咀嚼感)
・温感、冷感
・舌の奥が引き締まる感じ(収斂味=渋み)
・ピリピリとした痛覚(辛味)
・アルコールなどの、喉が焼けるような感じ
などがあります。
過去の記事でも書いたかもですが……私はマリアージュにおいて、食感をとても大切にしています。
実は食感については、今までのペアリング論ではあまり重要視されていなかったようです。
最近ではフードペアリングや飲み物とのマリアージュで「食感を変化させること」が大切だと言われていますね。

抹茶プリン×ヱビス華みやびとか、シーザーサラダ×ベルジャンホワイトのような食感の変化は好例です。
同じ重みで似たような味わいのものを合わせるのも良いですが、全く違うものを合わせてシナジーを創り出すのも、マリアージュの醍醐味です!
味覚
これが、一番イメージされる“味”ですよね。舌にある味蕾(みらい)という器官で感じとっているとされています。
基本の五味には、
基本の五味
苦味
甘味
塩味
酸味
旨味
の5つがあります!
『フードペアリング大全』では、この他に
〇アルコール
〇脂肪
〇辛味
の3つが追加されています。
また別の書籍(ビールのペアリングがよくわかる本/野田磯子先生)では、基本の五味の他に
〇焦げ味
〇辛味
も追加されていますね。
渋味や辛味は前述の通り触覚で感知しているので、純粋に味わいとは言い難いですが……
いろいろな前提条件がありますが、基本の五味さえ抑えていればOKです!!
嗅覚
これが今回の記事の本命です!匂いを感じる器官は鼻の奥にありますね。
香りには、
香りの種類
・嗅いで感じる上立ち香(オルソネイザル、ビール界隈でよく使う言葉では『アロマ』)
・飲み込んだあとに鼻に抜ける含み香(レトロネイザル、ビール界隈の言い方では『フレーバー』)
の2つがあります!
この違いは大切ですね。
私も、これまでの記事においても意識して使い分けています!
香りには強さと持続時間があります。
アロマは強い香りを感じやすく、フレーバーは持続時間が長いものを感じやすくなります。
また体温に触れると温度も上がるので、前面に出てくる香りも変わってきます。
だから、最初の印象と最後の余韻が全然違ってくるんですね。
ペアリングを考えるときも、アロマとフレーバーどちらも考慮に入れる必要があります。
「おいしい」における“香り”の重要性
まずは「味」「味わい」「風味」という言葉の違いについて。
味:味覚のみ
味わい:味≧香り
風味:味≦香り
「味」は、基本の五味の組み合わせのみです。
“甘味と苦味があって、そのバランスが取れている”ーとかですね。
「味わい」と「風味」はほぼ同じ意味です。
強いて違いを言えば、上記のように味覚か嗅覚のどちらに重きを置いているか?程度のニュアンスの差ですね。
味は、基本的には5種類しかありません。
しかし香りは、無数に(ビールについて表現できる香気成分だけでも300ほど)あります。
それゆえに人間の脳は、味わいの記憶を嗅覚に頼っているんです!
目隠しをした上で鼻をつままれると、何を食べているかわからない!というのは有名ですね。
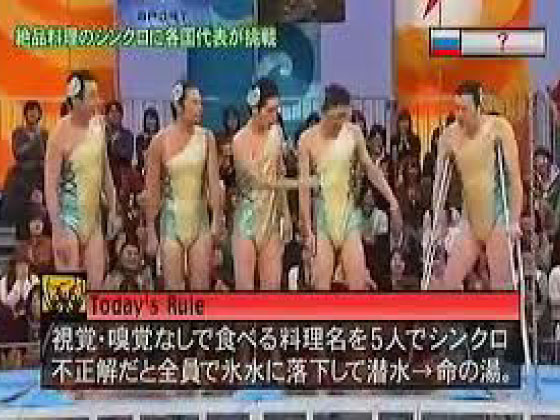
また嗅覚は、脳の中でも本能に近い部分で処理されています。口に入れるものは生死に関わりますからね。
焦げているとか、苦いとかアルコールが入っているとかの味覚で処理されるものは慣れれば食せますが、匂いを嗅いでみて「あ、やばい」と思うものは、腐っているとか、本当に食べたらダメなやつですよね。
味わいにとって、匂いが本当に大切だということがわかってもらえたかと思います!!
次は、香りを使ってフードペアリングをする方法について見ていきます!
香りを軸にしたフードペアリングのやり方!
『フードペアリング大全』には
“主要なアロマ分子を共有する食材どうしを合わせると美味になる”とあります。
そのアロマ分子とは、この後の辞典部分を見てねーってことなんですが。。
もう少し詳しく言うと、
・共通するアロマ分子を、同じ強さで持ってるものを合わせる
・基本の五味のうち、2つ以上を取り入れてバランスを取る
・食感のコントラストを意識する
のが大事、とのことです!!
その理論を使って、『フードペアリング大全』がおすすめするペアリングの一例を挙げると……
牡蠣×キウイ
チョコレート×キャビア
トマト×イチゴ
コーヒー×デミグラス
とのことです!
どのペアリングも、ビールでも表現できそうですね。
また試してみたら記事にしますね!
素晴らしい武器と新しい理論を手に入れて、いむらのマリアージュ力もさらにパワーアップしてきたのを実感します!!
今後の記事や、参加していただける方はフルコースのイベントでも、是非ぜひ今後のマリアージュを楽しみにお待ちくださいね!